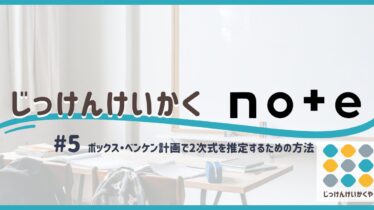 じっけんけいかくnote
じっけんけいかくnote #05 ボックス・ベンケン計画で2次式を推定するための方法
みなさんはどんなときに3水準以上の実験を行いますか?おそらく因子を変更することによる変化が直線(1次)なのか曲線(2次)なのかが知りたい場合が多いはずこのような場合は実験でデータを集めて直線もしくは2次関数で実験データを表現したいですよね仮...
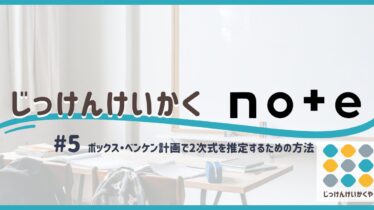 じっけんけいかくnote
じっけんけいかくnote 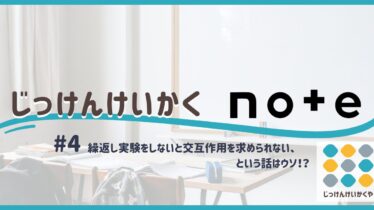 じっけんけいかくnote
じっけんけいかくnote 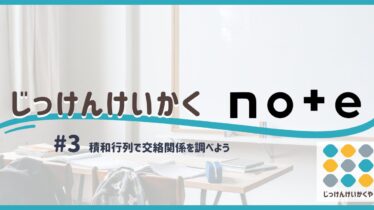 じっけんけいかくnote
じっけんけいかくnote 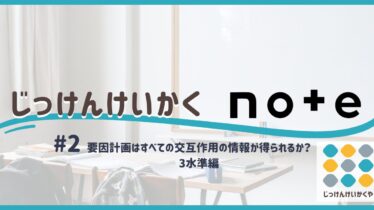 じっけんけいかくnote
じっけんけいかくnote 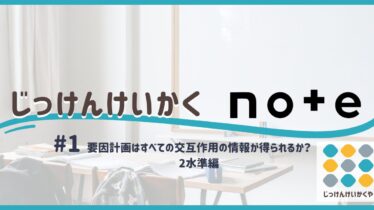 じっけんけいかくnote
じっけんけいかくnote