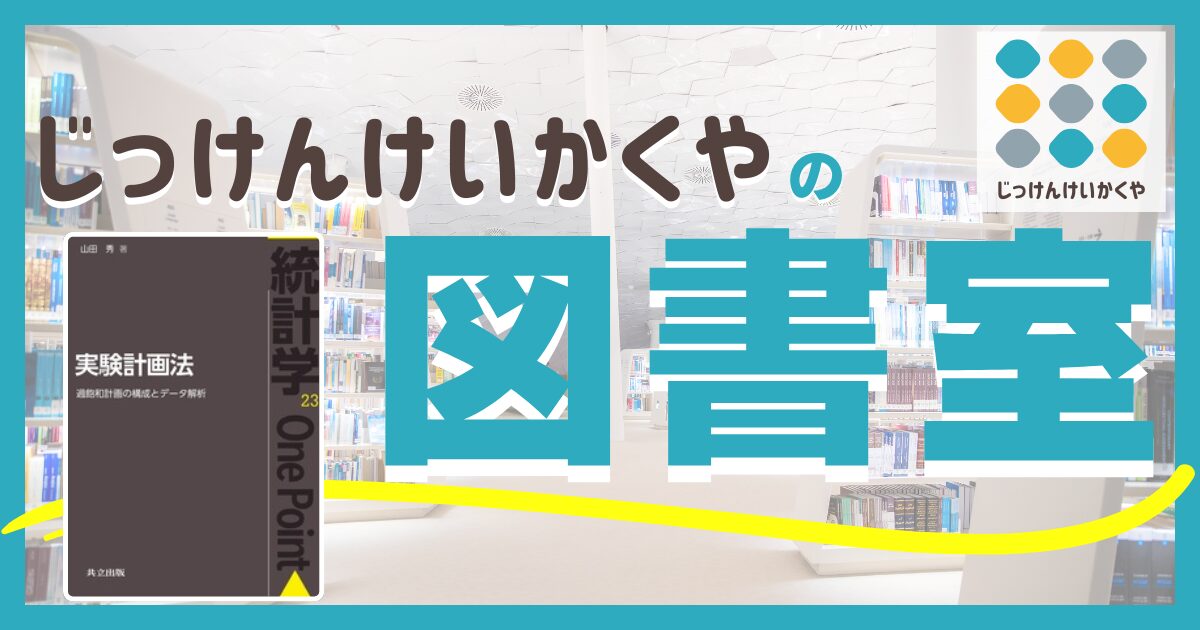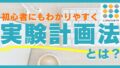じっけんけいかくやの図書室から、山田秀「実験計画法:過飽和計画の構成とデータ解析」をご紹介します。
こちらの本を紹介
¥2,420 (2025/07/13 17:48時点 | Amazon調べ)
| ジャンル | 実験計画法 |
| こんなひとにオススメ | 実験計画法の全体像を把握したい人 過飽和計画に興味があるひと |
| 必要な前提知識 | 第1章まで 統計学の基礎 第2章以降 線形代数 |
| 理論 or 実践 | 理論メイン |
内容の紹介
過飽和計画(supersaturated design)とは、一部実施要因計画の1つで、実験で推定しようとする母数の数が実験回数よりも大きな計画である。
本文 第2章より
通常、直交表などの一部実施要因計画は実験で推定しようとする母数の数(≒直交表の列の数)が実験回数(=直交表の行の数)よりも小さくなっています。(例えば直交表L8は8行、7列)
過飽和計画とは直交表の限界を超えて、実験回数以上の因子の影響を調べてしまおう!という計画ですね。
本書ではその性質について紙面の大半を割いて丁寧に説明されています。過飽和計画の詳細を知りたい方はぜひお手に取ってみてください。
タイトルに実験計画法と銘打っていますが、メインは第2章以降の過飽和計画の説明。最終章である第4章まで進まないと具体的な使用方法が紹介されないため、実践向きというよりは理論の解説が主軸となっている印象です。
実験計画法の基礎的な内容は第1章に凝縮されているので、実験計画法の全体像を把握したい方にもオススメできそうです。
必要な前提知識
第1章では正規分布やt分布の記述がみられますので、統計学に関する基礎知識がある程度必要です。
第2章以降は過飽和計画の性質の説明のために行列の計算が繰り広げられます。
目次
- 第1章 実験計画法とは
- 1.1 実験計画法の原点と基本
- 1.1.1 技術開発における実験計画法の役割
- 1.1.2 重要な用語
- 1.1.3 実験計画法の3つの原則
- 1.1.4 要因計画とは
- 1.1.5 データ解析に用いるモデル
- 1.2 直交表による要因計画の一部実施
- 1.2.1 一部実施要因計画の考え方と直交性
- 1.2.2 交互作用の求め方
- 1.2.3 直交表による一部実施要因計画の構成
- 1.2.4 2水準直交表による計画:生産量向上実験の計画例
- 1.3 直交表データの解析
- 1.3.1 分散分析による要因効果の検定
- 1.3.2 要因効果の推定
- 1.3.3 2水準直交表のデータ解析:生産量向上実験データの解析例
- 1.4 定義関係に基づく一部実施要因計画の構成
- 1.4.1 概 要
- 1.4.2 一部実施要因計画の構成と別名関係の把握
- 1.4.3 計画のレゾリューションと一部実施要因計画の構成
- 1.5 いくつかの一部実施要因計画
- 1.5.1 プラケット・バーマン計画
- 1.5.2 混合水準直交表
- 1.1 実験計画法の原点と基本
- 第2章 過飽和実験計画の概要と評価基準
- 2.1 過飽和実験計画とは
- 2.1.1 2水準のモデルと計画の概要
- 2.1.2 過飽和実験計画の発展
- 2.2 2水準過飽和実験計画の評価尺度
- 2.2.1 列間の直交性の評価
- 2.2.2 計画全体の直交性の評価
- 2.3 内積の二乗和の期待値E(s2)の性質
- 2.3.1 E(s2)の下界
- 2.3.2 E(s2)の下界の意味
- 2.3.3 E(s2)の下界の改善
- 2.4 多水準過飽和実験計画の評価尺度
- 2.4.1 列間の直交性の評価
- 2.4.2 計画全体の評価
- 2.4.3 列間のχ2 値に関する性質と下界
- 2.4.4 田口の殆直交表の直交性評価
- 2.5 混合水準過飽和実験計画
- 2.5.1 混合水準過飽和実験計画とは
- 2.5.2 計画全体の直交性の評価
- 2.1 過飽和実験計画とは
- 第3章 過飽和実験計画の構成と評価
- 3.1 行の入れ替えによる構成とその評価
- 3.1.1 確率対応法
- 3.1.2 行の入れ替えの基本的な考え方
- 3.1.3 E(s2)最適な計画(N = 12)
- 3.1.4 E(s2)最適な計画(N = 20)
- 3.1.5 3水準過飽和実験計画の構成
- 3.1.6 混合水準過飽和実験計画の構成
- 3.2 プラケット・バーマン計画の半分実施
- 3.2.1 構成方法と例
- 3.2.2 半分実施の2べき乗計画への適用
- 3.2.3 直交性の評価
- 3.3 プラケット・バーマン計画の交互作用による構成方法
- 3.3.1 交互作用列の追加によるWu (1993) の構成
- 3.3.2 割り付けた主効果と2 因子交互作用の完全交絡を避ける構成
- 3.4 特定の構造を取り入れた構成とその評価
- 3.4.1 2水準過飽和実験計画の構成
- 3.4.2 混合水準過飽和実験計画の構成
- 3.1 行の入れ替えによる構成とその評価
- 第4章 過飽和実験計画データの解析
- 4.1 データ例と最小2乗法に基づく解析
- 4.1.1 ラジコンシミュレータデータの解析例
- 4.1.2 Williamsの化学工程データの解析例
- 4.2 第1種,第2種の誤りの評価
- 4.2.1 評価方法
- 4.2.2 効果のある因子の選択確率の評価結果
- 4.2.3 Williams のデータ解析についてのコメント
- 4.3 いくつかの解析方法とそれらの比較
- 4.3.1 LASSOによる解析
- 4.3.2 計画と解析方法の組合せに関する評価
- 4.4 田口の確率対応法
- 4.4.1 概 要
- 4.4.2 数値例
- 4.4.3 解 説
- 4.1 データ例と最小2乗法に基づく解析
- 参考文献
- 索 引
¥2,420 (2025/07/13 17:48時点 | Amazon調べ)
更新履歴
2025/7/20 公開